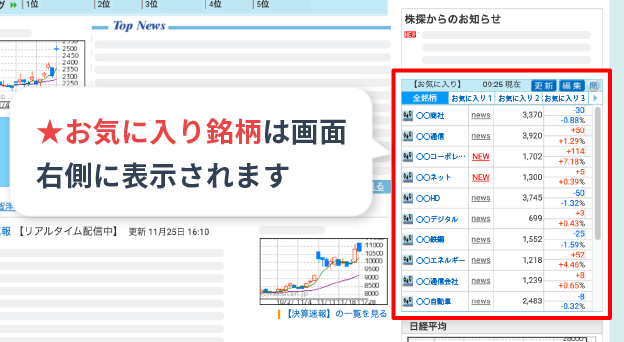【植木靖男の相場展望】 ─日経平均4万円達成の後始末は?
「日経平均4万円達成の後始末は?」
●2つの懸念材料は本物か
日経平均株価は4月19日以降、反発局面に入ったが、4万円の壁は厚く、多くの投資家が注目する75日移動平均線(6月7日時点3万9000円)すら上抜くことができず、混迷ぶりが顕著である。
だが、一方ですぐには崩れそうもない。それはなぜか? 同質の指数である米ナスダックが史上最高値を更新するほどの力強さを保っているからだ。これは裏を返せば、ナスダックが天井打ちすれば、日経平均株価も同調するということだ。エヌビディア<NVDA>を筆頭に米国のハイテク株の頑張りにより、日経平均株価は崩落を免れているともいえる。
では、本当に大丈夫なのか。ここに2つの懸念材料が浮上している。1つは、米長期金利が緩やかながら低下トレンドにあることだ。これまでだったら、金利上昇はハイテク株には逆風であった。しかし、いまは金利低下の方が気になるのだ。米国景気が沈みつつあるとの見方だ。ここへきて米景気指標は悪化傾向にある。米連邦準備制度理事会(FRB)の想定より早く利下げがあるとすれば、それは株価にとってプラスというよりマイナスの影響、つまりスタグフレーションを気にしなくてはならないということだ。市場が期待するソフトランディングが空鉄砲に終わる可能性である。
もう1つの懸念材料は、為替だ。米国景気が悪化し、想定外の利下げが必要になると、日米金利差が縮小し、円高・ドル安のベクトルが強まる。これは株価にマイナスとみる市場関係者は多い。実際、円安でメリットを受ける国内の上場企業は数多い。
だが、果たしてそうか。マネーの流れからすると、米国金利が急低下すれば、どうなるのか。わが国の日銀は利上げ方向だ。マネーは金利の高い方に流れる。つまり、日本から米国に長い期間、流出していた巨額のマネーが戻ってくることになる。度々指摘しているように、マネーが入ってくる国の経済は繁栄するのが基礎の基礎である。つまり、わが国の株価は、それによって上昇を強めると読める。
こうしたマネーの流れだけではない。台湾積体電路製造(TSMC)<TSM>について「熊本第3工場建設に含み」との報道がなされている。こうした外資の導入は今後一段と高まるとみてよい。
●バリュー株メインに出遅れ株に注目
とはいえ、当面の株価はどうかといえば、いささか複雑である。日経平均株価は昨年末から今年3月にかけて急上昇し、4万円の大台を突破した。その後、調整局面を迎えているわけだが、この4万円まで急騰した後始末がまだ終了していない。
しょせん相場は上がれば下がり、下がれば上がるのが基本だ。だが、現在の調整局面が上昇に転じるのには、しばらく後始末の時間が必要と言えそうだ。
いまは昔と違って信用取引のウェイトは小さいとみれば、3カ月、6カ月といった期間はあまり株価に大きな影響はないはずだが、依然、この期間の持つ重みは変わっていない。したがって、市場関係者の間では高値圏から3カ月後の7月から6カ月後の9月頃まで調整とみる声が強いようだ。
こうした雰囲気の中での物色対象はどうなのか。中長期ではここ数年続いたグロース株はお休みとなるとすれば、バリュー株がメインにならざるを得ない。もちろん、ハイテク株を中長期的に持続するのは問題ない。
一方、短期投資家はどうだろう。本来、短期投資家は理屈よりもチャートに頼ることが普通だが、この手法はなかなか難しい。何が難しいか? 投げが人より早くできるかにこの手法の成否はかかっているのだ。極端にいえば買い値より1円でも下がれば売りの姿勢だ。これしかない。
さて、話を戻そう。ここでの注目株だが、目先的には名村造船所 <7014> [東証S]、安田倉庫 <9324> [東証P]、メルカリ <4385> [東証P]など。これらは出遅れているだけに、チャンスが巡ってくることに期待したい。
2024年6月7日 記
株探ニュース

 米株
米株