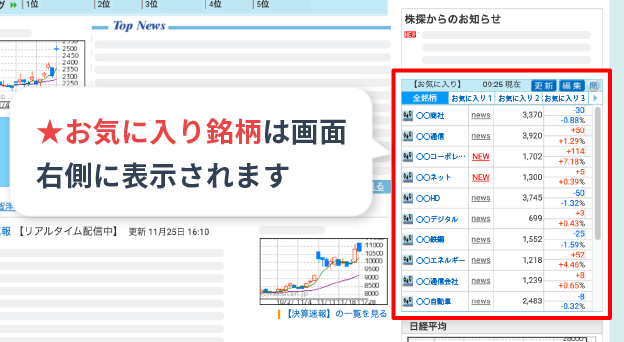TKP Research Memo(6):2023年2月期上期は大幅な増収及び営業黒字化を達成
■決算概要
2. 2023年2月期上期の連結業績
ティーケーピー<3479>の2023年2月期上期の連結業績は、売上高が前年同期比16.8%増の25,655百万円、営業利益が1,928百万円(前年同期は498百万円の損失)、経常利益が1,651百万円(同746百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失が102百万円(同2,133百万円の損失)と大幅な増収及び営業黒字化を達成した。また、重視するEBITDAについても、同102.6%増の4,624百万円と大きく回復している。
売上高については、コア事業であるTKP事業及び日本リージャスがともに増収となった。TKP事業は、採用研修需要の獲得により第1四半期が順調に滑り出すと、第2四半期も夏期講習や宿泊の需要を取り込み、回復基調が継続している。一方、日本リージャスについても、レンタルオフィス需要の回復とともに施設稼働率が伸長し、第1四半期、第2四半期と過去最高売上高(四半期ベース)を連続更新した。
TKP事業のサービス別売上構成比を見ると、「会議室料」が48.0%、「オプション」が18.8%、「料飲」が5.1%、「宿泊」が22.0%、「その他」(キャンセル料含む)が6.1%となっている。貸会議室や宿泊需要の戻りとともに、「会議室料」及び「宿泊」の回復が顕著となっている。
損益面に目を向けると、TKP事業については、売上高の一定の回復に加え、収益体質の強化により大幅な営業増益(前年同期比10倍以上)を達成し、EBITDAも大きく増加した(前年同期比約3.4倍)。一方、日本リージャスについては、2022年2月期第3四半期からのIWG※のフランチャイズ費用増加(減免期間の終了)や、顧客関連資産償却費及びのれん償却費が会計上の負担となっているものの、それらの影響を除いた調整後営業利益や調整後EBITDAは大幅に増加しており、市場における優位性そのものが失われたわけでなない。
※世界でリージャスブランドを展開するIWG plcのこと。
財政状態については、固定資産の圧縮等により、総資産が前期末比4.6%減の106,106百万円となった。一方、自己資本は37,951百万円とほぼ横ばいで推移したことから、自己資本比率は35.8%(前期末は34.0%)に改善した。また、手元流動性(現金及び預金)も12,361百万円を確保しており、財務基盤の安全性は確保されている。
(1) TKP事業の業績
売上高は前年同期比19.5%増の14,727百万円、営業利益は同972.4%増の2,533百万円、EBITDAは同237.5%増の3,154百万円と、売上高の一定の回復や収益体質の強化により大幅な増益となり、EBITDAも大きく増加した。これまで控えられていた企業の採用研修需要を含め、貸会議室需要の大幅な回復や新型コロナワクチンセンター・新型コロナウイルス感染者用宿泊療養施設/感染対策用施設としてのホテル貸出も寄与し、第1四半期が順調に滑り出すと、第2四半期についても夏期講習や宿泊の需要を取り込み回復基調が継続した。損益面では、増収効果に加え、これまで取り組んできた不採算施設からの撤退や周辺サービスの整理など収益体質の強化が奏功し、大幅な営業増益を達成した。2施設の新規出店を行った一方で、1施設を退店した結果、2022年8月末の施設数は239施設となった。
(2) 日本リージャスの業績
売上高は前年同期比10.8%増の9,511百万円、償却前営業利益※1は同38.2%減の438百万円、EBITDAは同22.3%減の832百万円と、増収ながら償却前営業利益及びEBITDAは減益となった。コロナ禍以降にオープンした施設の平均稼働率が好調に伸長し、売上高は第1四半期、第2四半期と過去最高(四半期ベース)を連続更新した。平均稼働率(全施設)は第1四半期が71.2%(前年同期は67.4%)、第2四半期が71.7%(同69.8%)と、積極的に稼働面積を広げながらも着実に上昇してきた。一方、償却前営業利益及びEBITDAが減益となったのは、2022年2月期第3四半期からIWGへのフランチャイズ費用が増加(減免期間が終了)したことが主因である。もっとも、その影響を除いた(調整後)営業利益※2では同34.4%増、調整後EBITDAでは同27.0%増とそれぞれ伸びており、市場における優位性そのものは失われていない。3施設の新規出店を行った一方、1店舗を退店した結果、2022年8月末の施設数は172施設となった。
※1 償却前営業利益とは、日本リージャス買収に伴う顧客関連資産償却費及びのれん償却費控除前の営業利益であり、買収に係る会計上の影響を取り除いたもの。なお、日本リージャス買収に伴う顧客関連資産償却費及びのれん償却費の合計は1,101百万円となっている。
※2 償却前営業利益から、さらにフランチャイズ費用の引き上げによる影響を取り除いたもの。前年同期と同条件で比較することにより市場ベースでの収益性の変化を見ることができる。
3. 2023年2月期上期の総括
以上から2023年2月期上期を総括すると、コロナ禍が継続するなかでも、Withコロナ(新型コロナウイルスとの併存)の定着による社会経済活動の正常化とともに、主力である貸会議室需要や宿泊事業が回復基調をたどり、大幅な増益を実現したことは、改めて同社の事業モデルの強さを実証するものとして評価できる。特に、コロナ禍においてもコア事業の施設や顧客基盤を維持するとともに、収益体質や財務基盤の強化にも取り組み、体力を温存してきたことが、今後の再成長に向けても大きなアドバンテージとなっている。さらには、コロナ禍をきっかけとして、オンライン配信を含めた案件単価の向上や、顧客ポータルシステムの開発、高付加価値化の推進など、今後の戦略の軸を打ち出したことについてもプラスの材料と言えるだろう。また、日本リージャスについても、フランチャンズ費用の引き上げによる影響を除けば、着実に収益基盤の底上げができており、今後はいかにスケールさせることで費用を吸収していくのかがポイントとなる。したがって、ブランド力を生かしたサブフランチャイズ展開へと舵を切った点は、営業や財務の制約を受けずに、地方での出店を加速する戦略として理に適っている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫)
《NS》
提供:フィスコ

 米株
米株