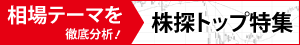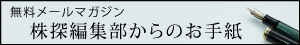【市況】中村潤一の相場スクランブル 「正念場迎えた上昇相場」
 株式経済新聞 副編集長 中村潤一
株式経済新聞 副編集長 中村潤一株式経済新聞 副編集長 中村潤一
2016年相場は大発会から前日(1月12日)まで日経平均が6連続安と、暖冬どころか凍えるような地合いで、しかも6日間で1800円を超える下げをみせたとあっては、投資家の嘆息もやむなしというところ。13日は満を持しての反騰となりましたが、現時点ではまだ自律反発の域を出ていない状況です。
●ターニングポイントを見極める
ひとたび境界線を突き破ると合理的ではない方向に加速するというのが相場の潜在意識に眠るDNA。年明けから東京市場はその典型といってよい試練に遭遇したといってもよいでしょう。ただ、行き過ぎた振り子は必ず戻るというのが相場の特性でもあります。千尋(せんじん)の谷底に丸太を転がすような下落局面も、あとで顧みれば買い場となっているターニングポイントが確実に存在するのです。
それを念頭に置いたうえで、値上がりと値下がり銘柄数から相場の体温を測定する騰落レシオにスポットを当ててみるとひとつのヒントが導き出されます。
東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は1月12日時点で57.9%。騰落レシオが60%を下回るのは非常に稀有な事態であり、12年の6月4日(59.3%)以来3年7ヵ月ぶりのこと。さらに今回の騰落レシオを下回る水準を記録したのは、さらにさかのぼって、09年11月27日につけた57.7%以来6年2ヵ月ぶりとなります。
では、この過去2回の騰落レシオ60%割れの後、相場はどうなったか。
●60%割れ後1ヵ月で過熱領域まで浮上
12年6月4日のケースでは、そこから一貫して騰落レシオは上昇に転じ、約1ヵ月後の7月9日には136.9%と過熱警戒域の120%台を17%も上回る水準まで浮上しました。この間の日経平均は8295円から8896円まで7.2%の上昇をみせています。
一方、09年11月27日のケースでも、その後大きく地合いが改善し、やはり約1ヵ月強を経た翌10年1月6日に127.6%と120%超えまで回復しています。この間の日経平均は9081円から1万731円まで18.2%の急速な戻りを演じました。
相場は個別のファンダメンタルズや外部環境に支配されているようで、時間軸にこだわらなければ結局は往来する振り子に相似した波動を展開します。大勢トレンドの形成はマクロのあらゆる要素が絡み合いますが、比較的短い期間で振り子の振れ幅を見るのにこの騰落レシオはとても有効なのです。
元来、1月は新興市場などを中心に中小型株優位の構図が描かれやすい時期で、実際昨年末のフィンテック関連やドローン関連、自動運転車関連などの物色動向からもその傾向は読み取れます。しかし、年明けからの波乱相場に乗じて、臨機応変にETFや、日経平均に連動して下げた主力株などを仕込みの対象とするのも有力な投資作戦といえるでしょう。
●薄氷の24ヵ月移動平均線
さて、ここでもう一点、相場の大勢トレンドを見るうえで、月足チャートで外せない観点があります。テクニカル的に日経平均の長期波動の分水嶺として重要性の高い24ヵ月移動平均線を12日時点で割り込みました。13日の反騰でとりあえず小康を得ましたが、日経平均1万7500円近辺は正念場であることに変わりありません。
さかのぼって、24ヵ月移動平均線を上回ったのは、まさに民主党から自民党・安倍政権へと移行する12年12月のことであり、それ以降はここを下回ることなく日経平均は15年6月までの2年半でほぼ2倍となりました。その後は8~9月のチャイナ・ショックによる暴落にも耐え、1万6900円台でこの移動平均線がサポートラインとして見事に機能した事実があります。
この24ヵ月移動平均という足場が“アベノミクス相場”では大きな意味を持つと考えています。今後、再び激しい揺れに襲われ、下ヒゲでなく同移動平均線を明確に下抜けた場合は、アベノミクス相場の終焉が訪れている可能性も否定できず、その意味では用心が必要といえそうです。
原油価格の下落はシェール革命を背景としたパラダイムシフトがもたらせた結果とはいえ、商品価格全般の下落はデフレの潮流を意識させるもの。新興国経済に対する漠然とした不安を投影しているともいえます。世界株市場の動きは、日本・欧州・中国でのグローバルな金融緩和に対する催促相場の様相を呈しているようにも見え、このニーズを当局が汲み取り、政策に反映できれば眼前の暗雲は払拭できると考えています。
(隔週水曜日掲載)
株探ニュース

 米株
米株