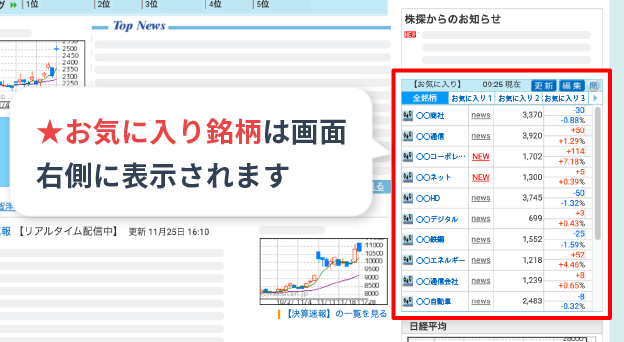Eギャランティ Research Memo(7):営業体制の強化と周辺分野への事業展開により成長目指す
■今後の見通し
2. 重点施策
イー・ギャランティ<8771>は2023年3月期の重点施策として、以下の2つの施策を推進している。
(1) 営業体制の強化
景気の先行き不透明感が強まるなかで、企業活動における不確実性を低減することを目的とした信用リスク保証サービスに対するニーズ増加に対応するため、営業人員の増員と早期戦力化に向けた取り組みを推進しているほか、地方顧客の開拓を推進すべく営業拠点の拡大を図っている。
営業人員については2021年3月期末の約50名から2022年3月期末は約70名と年々増強しており、2023年3月期は前期末比3割増の90名程度まで増員する計画となっている。2022年4月の新卒社員は40名弱となったが、大半は営業部門に配属されており、今後もニーズの増加に合わせて営業人員の増強を進める方針である。
また、若手社員の早期戦力化を図るため、2023年3月期より画一的な販売方法の導入と集中的な研修を実施している。従来、新規契約獲得のための販売手法は個々の営業スタッフの裁量に委ねられていたため、パフォーマンスにバラつきが生じていたほか、若手社員の戦力化にも時間を要していた。今回、こうした課題を解決するため、販売手法を標準化することにした。例えば、サービスの基本的な説明については、動画を作成して顧客に視聴してもらうようにしたほか、保証料の見積り手法の標準化、トークスクリプトの活用などにも取り組み、集中的な研修を実施することでこれらを浸透させている。導入後の効果として、若手社員の新規契約獲得率が上昇しており、ベテラン社員と遜色がなくなってきていると言う。戦力化までの期間については、従来2~3年掛かっていたが、1年に短縮することを目標にしている。こうした取り組みにより、営業人員1人当たりの生産性向上と新規顧客の獲得並びに保証残高の積み上げを図っていく。
一方、営業拠点の開設については2022年に入って5月に東北支店、6月に北陸支店を新たに開設しており、これらの地域での新規顧客開拓を推進している。地方拠点としてはあと1拠点の開設を視野に入れているようで、候補としては唯一空白地帯となっている中国・四国地方をカバーする拠点が考えられる。拠点開設に伴って固定費の増加が見込まれるものの、出張費がなくなることや生産性が向上することなども考えれば、利益面ではプラスに寄与しているようだ。
また、地方拠点においては提携先の金融機関とも協業しながら、それぞれの地域産業の特性に合わせた商品の開発も進める予定にしている。例えば、水産業や農業が集積している地域では一般企業とは異なる保証ニーズがあり、こうしたニーズに対応した商品を提供する考えである。
(2) 周辺分野の事業展開
周辺分野への事業展開を図るべく、企業間取引に関するデータ収集の強化を継続し、収集したデータを生かした速く精度の高い企業審査を活用したサービスの展開を推進する。
同社は現在、月間で3万社超の審査を行うため、対象企業の取引情報や信用情報など様々なデータを、1日当たり約260万項目以上収集し、データベース化している。これらのデータを活用して、2021年11月より新たに請求書発行・入金管理・代金回収といった事務業務のアウトソーシングサービス「eG Collect」、並びにそのオプションとなる債権買取サービス「eG Pay」を開始した。「eG Collect」は、顧客企業の取引先からの入金が支払期日よりも遅れた場合には、同社が取引先に代わって販売代金を支払うサービスであるため、顧客企業は売掛金の未回収リスクを抱えずに取引することが可能となる。また、「eG Pay」は顧客企業が売掛金を早期資金化したい場合に、同社が請求書を買い取り、申し込み日から3営業日目に顧客企業に代金を振り込むサービスである。顧客企業は後日、取引先から回収した販売代金を同社に振り込む流れとなる。同社は、政府系金融機関の資金繰り支援策の期限到来により、今後、倒産件数が増加することで、売上債権買取のニーズも増加すると見て販売を強化する方針である。
「eG Collect」「eG Pay」については、サービス開始以降2022年7月までに、提携関係にある地方銀行及び信用金庫の5割弱にあたる28行とビジネスマッチング契約を締結しており、これら金融機関で法人向けサービスの1つとして販売されている。現在は主にEC事業者向けを中心に販売が進んでいるもようで、2022年3月期の販売実績は数千万円程度だったと見られる。企業において請求書発行や代金回収業務等はアウトソーシング化のニーズが強いことや、今後倒産件数が増加してくれば債権買取ニーズの増加も見込まれることから、これらサービスの成長余地は大きいと見られ、今後の動向が注目される。
信用リスク保証サービスに対する潜在ニーズは大きく、中長期的に成長が期待できる企業として注目
3. 中期見通し
同社は中期の経営数値目標として、連結経常利益50億円をターゲットとしている。これを達成するために必要となる保証残高は2022年3月期末から1.3倍の規模となる7,500~8,000億円が目安となり(平均保証料率、経常利益率が一定と仮定した場合)、順調に進めば2025年3月期にも達成できる見通しだ。
なお、同社の提供する信用リスク保証サービスは、国内景気が悪化する際にニーズが増大するため、好景気の局面では伸び悩むと思われがちだが、好景気の場合にも伸びるビジネスモデルとなっていることが特徴と言える。好況の場合は企業の売上拡大によって売上債権も増加すること、また、新規事業を開始する企業も増えるため、こうした事業に対する保証ニーズも増加するためだ。前述したように売上債権の国内市場規模は200兆円超と膨大であり、新規顧客の開拓余地が大きいこと、同様のサービスを提供する競合企業がまだ台頭しておらず、営業体制を強化すれば保証残高も積み上がる状況にあることから、今後も年率10%台のペースで利益成長を継続していくことは可能と弊社では見ている。
さらに、コロナ禍が収束すれば海外展開を進めることも視野に入れており、既にそのための人材を獲得するなど準備を進めている。国内の成功モデルを踏襲し、海外でも現地金融機関と連携して、日系企業の現地法人向けにサービスを展開していくことになりそうだ。長期的に見ても、周辺事業における新規サービスの育成など、収益ポートフォリオの拡充による成長が期待でき、今後も持続的に成長が見込まれる企業の1つとして注目される。
リスク要因としては参入企業の増加による競争激化が挙げられるが、前述したように企業のリスク評価を適正かつ迅速に行うための情報収集力と分析力が競争力の源泉となるサービスだけに、先行して膨大な信用情報を蓄積し、与信審査を行うシステムを構築した同社の先行者メリットは大きく、今のところそのリスクは極めて低いと弊社では考えている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
《SI》
提供:フィスコ

 米株
米株