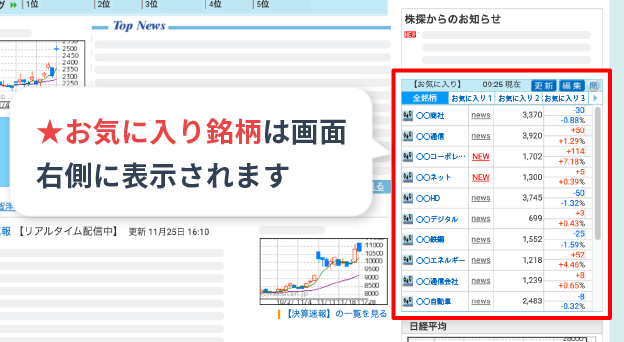バードマン Research Memo(4):MX事業が収益の土台を築きながら、2021年からエンタメ市場へ進出(2)
■事業概要と市場動向
3. エンタメ市場概要
Birdman<7063>が属するエンタメ市場動向について、(一社)コンサートプロモーターズ協会の調査データをみると、音楽ライブの1公演当たり指標(入場者数、売上高、入場単価)において、入場者数は2011年に1,504人だったが、そこから2013年までは増加トレンド、その後は横ばい傾向となったが、2020年にコロナ禍により1,021人、2021年に866人へと激減した。1公演当たり売上高についてもほぼ同様の動きとなっており、2011年は1公演当たり865万円の売上高、その後はおおむね横ばい傾向だったが、2020年に732万円、2021年に580万円まで落ち込んだ。1入場者当たりの単価(入場単価)は、2011年の5,755円から増加傾向が続き、2019年に7,398円まで増加したが、2021年には6,699円まで落ち込んでいる。
また、1社当たりの音楽ライブ公演数や売上高などの指標をみると、1社当たり公演数は2011年の329公演から2015年の477公演まで増加トレンドとなり、その後は横ばい傾向、そしてコロナ禍の影響で2020年に148公演へ激減したものの、2021年は361公演へ回復している。また、1社当たり売上高は、2011年の28.5億円から2019年の53.1億円までおおむね増加傾向で、2020年に10.8億円へ大きく減少し、2021年は21.0億円へ若干回復を示した。音楽ライブの集客や売上高はコロナ前と比べると引き続き低迷しているが、ライブ運営会社は公演回数を増やす努力をすることで売上高の確保を図っている。実際には、ライブ公演の収容人数制限(収容上限キャパシティの50%など、自治体により異なる)等の問題から、苦肉の策として公演回数を増やすことで集客を確保している可能性も垣間見える。政府は既に新型コロナウイルスの感染症法上の分類を2023年5月8日から「5類」に移行することを決定しており、イベントに関する規制や制限も撤廃される見通しだ。そのため、ライブ・エンターテインメント市場においては2023年後半から2024年にかけて本格的な市場回復が期待されるだろう。
4. エンタメ市場への参入と収益獲得機会
ライブ・エンターテインメント市場がコロナ禍で低迷するなか、まさに渦中にあった2021年9月(2022年6月期)から「EX事業」を新設し、エンタメ市場へ参入したことは注目に値する。当時は2020年10月15日にK-POPの筆頭格である「BTS」が所属する芸能事務所のビッグヒットエンターテインメント(現HYBE)が韓国証券取引所に上場し、時価総額が一時、日本円換算で1兆円を超えるなど、コロナ禍にあっても著名アーティストを要するプロダクションが注目を浴びていた時期でもある。また、当時、BTSが開催した有料オンラインコンサートで191ヶ国や地域からのべ99万人が視聴したことも話題となっており、デジタル技術を活用したエンタメDXの拡大という収益チャネルの多様化がファンや利用者獲得の起爆剤となったケースとしても注目される。同社は既にMX事業においてもデジタルを強みとした差別化を進めており、新たに参入したエンタメ市場においてもこの強みを生かし、世界有数のライブ配信技術とクリエイティブを掛け合わせ、オフラインでは体験できない新しい映像・エンターテインメント体験が実現可能な「さわれるライブ5D LIVE」の事業化を推進している。MX事業とEX事業の親和性の深化という意味でも注目できるだろう。
同社のエンタメネクストを除く既存のEX事業においては、契約アーティストである「7ORDER」の活動費が主な売上高の構成要素となっている。その主な内訳としては、ライブ開催に伴うチケット収入、ファンクラブ会員費、グッズ販売収入などが挙げられるが、まだ発足して間もないこともあり、現在はライブ開催に伴うチケット収入が同社の売上高の過半を占めているとみられる。一方、7ORDERとのグロースパートナーシップ契約においては、利益の一定割合で按分するレベニューシェア形態が取られており、この契約内容に基づいた収益配分がアーティスト側にされている。アーティスト側にとってもそれまでよりメリットの大きい報酬形態となっており、同社と7ORDERとは双方にとってWIN-WINの良好な関係が構築されているとみられる。また、現在はライブ開催による収入が売上高の中心となっているが、今後は粗利率の高いファンクラブ会員費やグッズ販売による収益が増加することが予想され、収益源の多様化が進み、利益率についても上昇することが見込まれよう。
同社のEX事業(除くエンタメネクスト)の売上高は7ORDERのライブ開催に伴うチケット収入の割合が大きいため、音楽ライブの公演スケジュールや観客動員数が収益ドライバーとなる。同社とグロースパートナーシップ契約を締結した2021年9月以降のライブ公演スケジュールをみると、2021年11月27日~2022年2月27日にかけて開催された7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」が同社発表による観客動員数が85,000人となっており、この公演のチケット単価は公表されている一般発売向けでぴあアリーナMMと国立代々木競技場公演のみが税込み9,800円、それ以外の公演は9,300円だったことを踏まえると、当該ライブからのチケット収入は単純計算で85,000人×入場単価10,000円で850百万円程度に達していたとみられる。また、2022年6月期はこの大型ツアーを第2四半期と第3四半期で開催したことに加え、第4四半期にはグループ結成3周年イベントも開催、この2つのイベントで合計10万人超を動員したとしており、これらが同社の2022年6月期のEX事業における売上高1,289百万円の主な構成要素となっていると推測される。
なお、EX事業における主なコスト項目としては、(1)ライブ実施時に要する会場代や演出等に要する費用、(2)グロースパートナーシップ契約に伴い、契約アーティストに支払う費用、の2つが大きく挙げられる。1つ目のライブ実施に必要となる会場代などの費用は実際の集客数に連動しない固定費的な位置づけであり、2つ目のグロースパートナーシップ契約に伴い発生するレベニューシェアについては集客数に連動する変動費的な位置づけとなるとみられる。一般的に会場・付帯設備費やスタッフの人件費、コンサート製作費、宣伝費、イベンターへ支払う外注費などの固定費は、ライブ会場の実際の観客数にかかわらず一定額、発生する費用となるため、今後、コロナ禍からの経済正常化の流れのなかで1ライブ会場当たりの収容人数が増加すれば(すなわち、コロナ禍のときと比べて少ない会場や公演数で同規模の観客動員が可能となれば)、売上高に占める固定費が減少し、1ライブ当たりの利益率が大きく上昇する可能性がある(2022年6月期のEX事業における売上高1,289百万円、セグメント利益219百万円、セグメント利益率17.0%)。
また、同社では7ORDERのファンクラブも開設しており、月額会費制(税込495円、入会金なし)としている。7ORDERのファンクラブ会員数は公表されていないが、比較対象となり得るジャニーズ系の主要な男性アイドルユニットのファンクラブ会員数はYouTubeやTwitterなどの登録者数及びフォロワー数と高い相関を有している。7ORDERのYouTube登録者数やTwitterフォロワー数が10万人を超えており、この登録者数やフォロワー数が増加傾向にあることなどを踏まえると、向こう数年以内に7ORDERのファンクラブ会員数も10万人超へ増加する可能性もあるだろう。ファンクラブ会員費は年間あたり5,940円となるため、仮に10万人の会員を獲得できれば、ファンクラブ会員費だけで594百万円に達する試算となるうえ、ファンクラブ会員費は相対的にライブチケット収入などに比べると粗利率が高いとみられることから、EX事業への継続的な収益貢献も期待されよう。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 永岡宏樹)
《SI》
提供:フィスコ

 米株
米株