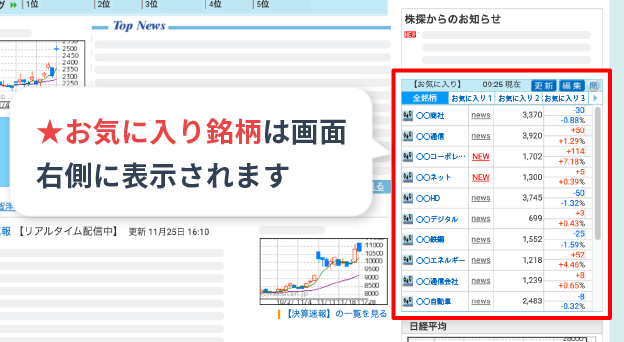ワコム Research Memo(6):2025年3月期も増収増益の見通し。「ブランド製品事業」の損失縮小見込む
■業績見通し
1. 2025年3月期の業績見通し
2025年3月期の連結業績予想についてワコム<6727>は、売上高を前期比1.0%増の120,000百万円、営業利益を同20.4%増の8,500百万円、経常利益を同13.7%減の8,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益(以下、最終利益)を同35.9%増の6,200百万円と増収増益(経常利益を除く)を見込んでいる。
売上高については、部材調達・生産の余剰に起因する負の遺産の整理に一定の目処がついた「ブランド製品事業」が、構造的な市場環境の変化に対応すべく、2026年3月期の黒字化を見据えたさらなる構造改革を進めながら増収を確保する想定である。一方、「テクノロジーソリューション事業」については現時点ではほぼ横ばいを見込んでいる。
損益面では、積極的な研究開発投資を継続する一方、前期までの利益を圧迫してきた「一時的な費用」の解消や構造改革(粗利改善やコスト最適化等)により「ブランド製品事業」の損失幅が縮小し、営業増益に寄与する想定となっている。経常利益が減益となるのは為替差益のはく落によるものであるが、特別損失がなくなることで、最終利益では増益を確保する見通しである。
(1) ブランド製品事業
売上高は前期比3.5%増の35,000百万円、セグメント損失は2,000百万円(前期は4,520百万円の損失)を見込んでいる。アップデートされた商品ポートフォリオ群の市場浸透を図るものの、市場環境の変化等を保守的に判断し僅かな増収にとどまる想定である。損益面では、前期までの「一時的な費用」の解消や現在認識可能な構造改革効果を前提に損失幅の縮小を見込んでいる。次期中期経営方針(Wacom Chapter 4)の初年度(2026年3月期)での黒字転換に向けて、構造改革をさらに進めていく考えだ。
(2) テクノロジーソリューション事業
売上高は前期比横ばいの85,000百万円、セグメント利益は同2.9%減の16,000百万円を見込んでいる。売上高はOEM提供先の動向を慎重に見極めるため、現時点では前期と同水準を想定している。損益面では、前期までの「一時的な費用」が解消する一方、将来に向けた積極的な研究開発投資の継続によりわずかな減益を見込んでいる。
2. 弊社の注目点
引き続き為替相場の動向や先行き不透明な経済情勢による影響には注意が必要であるが、同社の連結業績予想の前提には合理性があり、十分に達成可能であると弊社では見ている。保守的に見ている「テクノロジーソリューション事業」の伸びや、前期リリースした新製品の市場浸透が業績の上振れ要因となる可能性にも注意が必要である。また、損益面では、B/Sを中心に負の遺産の整理に一定の目処がたち、あとはP/Lにおけるオペレーション費用の最適化をいかに進めるかがカギを握るであろう。一方で、将来に向けた投資は継続する必要があり、メリハリを利かせた事業運営に注目したい。
中長期的な視点からは、「Wacom Chapter 3」のアップデートで掲げた「事業構造変革」(改編プラン)の進捗に注目したい。今後やるべきことがより具体的に明示されたことから、それぞれの成果をフォローするとともに、いかに「Wacom Chapter 4」での成長加速につなげていくのかを見定めたい。特に新コア技術(AI、XR、セキュリティのほか、リモートを含む)との組み合わせや新しいビジネスモデルの立ち上げが、中長期的な同社の方向性や将来性を占ううえで重要な判断材料になると見ている。そのためには、同社自身における技術開発はもちろんのこと、他社との連携により新しいサービスとしての価値をいかに生み出していけるかが成否を決することになると考えられる。また、これまでペン体験の各要素(ハード、ソフト、サービス、技術、コミュニティ等)を単体で提供し、それぞれに実績を積み上げてきたが、今後はそれらが一体となった「ペンの統合体験」として提供することで同社のアドバンテージがより高まるものと見ている。デジタルインクとAIによる新たな価値提案についても、すでに動き始めた教育分野以外にも様々な分野で可能性があり、他社に先駆けてデータやノウハウの蓄積が進めば、AIの深層学習機能を活用して個々のユーザーに深く向き合うことが可能となり、そこから新たな体験価値を生み出すことによって革新的な領域で圧倒的なポジションを確立できる公算も大きくなる。ターゲットとするデジタルコンテンツ制作、教育DX、ワークフローDXという3つの市場ドメインにおいて、ポテンシャルは各方面で広がっており、技術面やブランド力でゆるぎないポジションをキープしていくことが、それらを取り込んでいくために重要なファクターと言えるだろう。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫)
《HN》
提供:フィスコ

 米株
米株