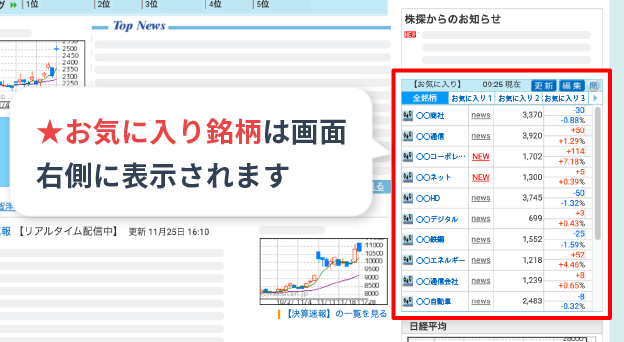ワコム Research Memo(5):「ブランド製品事業」は苦戦続くも、負の遺産の整理に一定の目処
■ワコム<6727>の決算概要
2. 事業別の業績概要
(1) ブランド製品事業
売上高は前期比17.8%減の33,814百万円、セグメント損失は4,520百万円(前期は3,981百万円の損失)と減収かつセグメント損失が拡大した。売上高は円安効果(約20億円の増収要因)があったものの、主力の「クリエイティブソリューション」が消費者センチメントの悪化等に伴う市場環境の変化により、ディスプレイ製品、ペンタブレット製品ともに販売が減少した。一方、「ビジネスソリューション」については流動的な市況の変化や案件進捗の影響があるなか、前期を上回ることができた。損益面では、前期に計上した棚卸資産評価損の戻入益の計上(約19億円)に加えて、販管費の削減等に取り組むも、減収による収益の大幅な押し下げや買付契約評価引当金の費用計上(約20億円)等により損失幅が拡大した。活動面では、商品ポートフォリオの刷新に向けて新製品※を導入したものの、既存モデルの在庫削減プロモーション(値下げ販売)との兼ね合いにより、立ち上がりはスローとなっている。
※「Wacom One」(エントリーモデル)では、2023年8月に新しい機能やサービスが付いた液晶ペンタブレットを発表したほか、「Wacom Cintiq Pro」(プロ向け)についても、2023年10月に「Wacom Cintiq Pro 17」及び「Wacom Cintiq Pro 22」を発表した。
a) クリエイティブソリューションの売上高
前期比21.1%減の29,170百万円と減少した。製品別に見ると、「ディスプレイ製品」がプロ向け及び低価格での新商品が売上高に貢献した一方で、既存モデルでの需要減少により減収となった。「ペンタブレット製品」についても、中価格帯での新商品が売上貢献したものの、プロ向けモデル及び低価格帯の既存モデルでの需要減少等により減収となった。
b) ビジネスソリューションの売上高
前期比10.2%増の4,644百万円となった。流動的な市況の変化や案件進捗による影響を受けたものの、前期を上回ることができた。
(2) テクノロジーソリューション事業
売上高は前期比18.7%増の84,981百万円、セグメント利益は同53.2%増の16,481百万円と増収増益となった。売上高は円安効果(約54億円の増収要因)に加え、「EMRテクノロジーソリューション」におけるOEM提供先の需要増が増収に寄与した。「AESテクノロジーソリューション」についても、市場環境の変化を受けつつも増収を確保した。損益面でも、前期に会計処理した買付契約評価引当金の費用計上(約20億円)が2024年3月期には同処理がなかったことや、増収による収益の押し上げ、さらに円安効果(約13億円の増益要因)等により増益となった。
3. 2024年3月期の総括
2024年3月期を総括すると、好調なOEM需要を背景とする「テクノロジーソリューション事業」の伸びにより増収増益を実現したとは言え、プラス要因となった円安効果やマイナス要因となった「一時的な費用」による影響が入り混じり、評価の難しい決算となった。それらを除くと、実質的には「ブランド製品事業」を中心に厳しい環境が続いたという見方が妥当であろう。後述するように、1) 新型コロナウイルス感染症の拡大(以下、コロナ禍)における「需要の先食い」解消の遅れ、2) 買い控え傾向の継続のほか、3) 他カテゴリーへの需要シフト傾向(選択肢の多様化)などが要因として挙げられるが、1) 及び2) のような景気循環的なものと3) の構造的な変化によるものとをしっかりと見極めるとともに、新たな技術の浸透やDXの流れといったメガトレンドにも注意を払う必要がある。2021年3月期以降の「ブランド製品事業」を振り返ると、コロナ禍における業績の急拡大とその反動による失速という波の大きさが目立つが、そこはならして考えたほうがよいであろう。むしろ、メガトレンドの動きを見据えながらターゲットとすべき市場ドメインを定め、それに向けた準備を進めていけるかがWacom Chapter 3の大きなテーマであったはずである。その意味では負の遺産の整理に一定の目処が立ち、今後の方向性がより明確になったところはプラスの材料として評価したい。また、新たなユースケースの提案や創作ワークフローのDX対応、デジタルインクサービスの立ち上げなど、将来に向けた基盤整備において具体的な事例が積み上がっており、その点も評価できるポイントと言える。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫)
《HN》
提供:フィスコ

 米株
米株