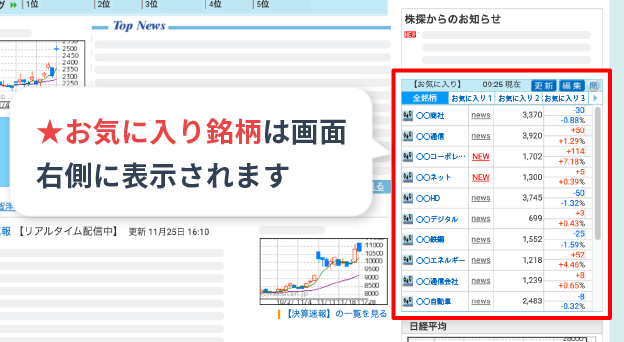ブランディング Research Memo(6):予算未達の要因分析と対策は実行済み
■業績動向
1. 2023年3月期の業績概要
ブランディングテクノロジー<7067>の2023年3月期の連結業績は、売上高5,163百万円(前期比4.5%増)、営業利益120百万円(同8.5%増)、経常利益122百万円(同11.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益79百万円(同2.5%減)と、2期連続の増収増益となった。
日本経済は、コロナ禍の影響が和らぎ、行動制限が徐々に緩和されて景気が緩やかに持ち直していく状況となったが、ウクライナ情勢の長期化や世界的な金融引締めなどを背景とした世界経済の減速懸念、急激な円安や物価高騰などによる国内景気への影響から、依然として先行き不透明な状況が続いている。同社の主要事業領域である国内インターネット広告市場は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大、ウクライナ情勢、物価高騰など国内外の様々な影響を受けつつも、社会のデジタル化を背景に好調な「インターネット広告費」の成長に支えられる格好となった。このような環境下、同社は、企業理念である「共存共栄の精神で世の中に新たな価値と笑顔を創出します」を実践し、中小・地方企業の経営者に対して真摯に向き合う事業推進パートナーとしてデジタルマーケティング事業とブランド事業に注力、継続的・安定的な事業規模の拡大を進めた。
この結果売上高は、第4四半期に大型プロジェクトの減額が発生したが、デジタルマーケティング事業の好調から4.5%の増収を維持することができた。営業利益は、大型プロジェクトの減額やブランド事業の採算低迷、円安などにより売上総利益率が低下したが、デジタルマーケティング事業の好調や人員増強局面ながら販管費を削減したことなどより、8.5%の増益を達成することができた。また、同社の優位性を支える「業界別に体系化されたノウハウ」の成果ともいえるホワイトペーパー数やセミナー数などが大きく伸びており、営業利益を安定して積み重ねる組織体制になってきたことも、増収増益を確保できた要因と言えよう。なお、2023年3月期の連結業績は、後述するようにブランド事業のセグメント利益の減少及び大型プロジェクトの減額により、売上高で87百万円、営業利益で38百万円の予算未達となった。ただし、アフターコロナでも中小・地方企業のデジタルシフトニーズが強く、ブランド事業と大型プロジェクト以外全般的に順調に業績が推移したこと、セグメント・ユニット事業構造により予算未達の要因分析を早期に完了して既に対策を講じていることから、ブランド事業のセグメント利益の減少及びデジタルマーケティング事業での大型プロジェクトの減額は短期的な影響にとどまる見込みである。
デジタルマーケティング事業が連結の増収増益をけん引
2. セグメント別の動向
セグメント別では、ブランド事業は売上高1,442百万円(前期比0.2%減)、セグメント利益283百万円(同15.1%減)、デジタルマーケティング事業は売上高3,555百万円(同6.2%増)、セグメント利益262百万円(同17.8%増)、オフショア関連事業は売上高165百万円(同14.3%増)、セグメント利益16百万円(同17.7%減)と、連結での増収増益をデジタルマーケティング事業が牽引した内容となっている。
ブランド事業では、業界別ノウハウの強化、同社とシナジーを生む企業との業務提携や共催セミナー開催などに注力したが、事業成長に向けた人材投資の成果が遅れたため減収減益となった。事業ユニット別では、事業ユニット1でブランド、外壁リフォーム、不動産の主力ユニットの営業体制強化、業界別ノウハウの発信を軸としたマーケティング強化による新規顧客獲得の効率向上、事業ユニット2では歯科・医療に特化したサポート体制の構築、学会を中心とした業界イベントなど独自の顧客獲得チャネルの強化、事業ユニット3では中堅企業向け新体制の構築、大型案件でのアップセル・クロスセルの強化を進め、特に事業ユニット3は順調に推移した。
デジタルマーケティング事業では中堅企業が好調だったほか、地方自治体及び公共団体のデジタルマーケティング支援に注力するなど顧客層の拡大が進んだ結果、大型プロジェクトの減額を吸収して増収2ケタ増益となった。事業ユニット4としては、採用により人員を強化し、自治体予算の獲得に向けた新チームを設立、一方で既存顧客へのクロスセル強化により利益率の向上を図った。また、習熟度向上、外部フリーランスの活用、ChatGPTの活用などによるフロント人材の生産性向上に努めた。
オフショア関連事業では、円安の影響によりVIETRYのグループ内ブランド事業に対する売上高が膨らんだものの、ベトナム国内で売上原価と販管費が増加したため増収減益となった。事業ユニット別では、事業ユニット5で沖縄県内のネットワークを活かした営業・マーケティング活動により優良顧客の獲得を進めた一方、事業ユニット6では円安進行で積極的な投資は控えつつ原価抑制・人材配置の見直しを実施した。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)
《SI》
提供:フィスコ

 米株
米株