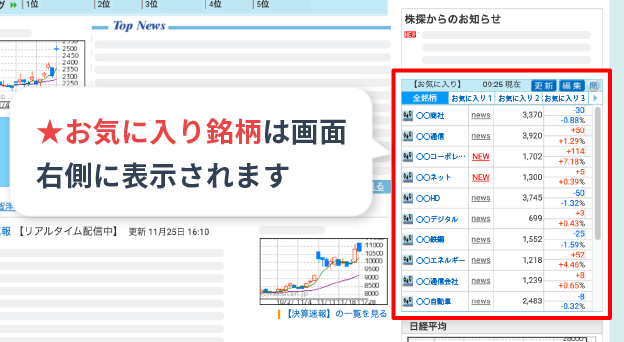三菱総研 Research Memo(4):2022年9月期第3四半期は売上高、営業利益、経営利益ともに過去最高を達成
■業績動向
1. 2022年9月期第3四半期累計の業績
三菱総合研究所<3636>の2022年9月期第3四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比14.0%増の91,673百万円、営業利益が同40.6%増の9,335百万円、経常利益が同41.6%増の10,430百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同54.9%増の7,819百万円となり、売上高、営業利益、経常利益は過去最高業績を達成した。増収増益の要因は、「中期経営計画2023」の各種施策の着実な実行だ。シンクタンク・コンサルティングサービスにおいては、成長事業として位置付けるDX関連事業を積極的に展開した。これにより、官公庁から5G関連、新型コロナウイルス感染症に係るAIシミュレーション、最先端ICT、省エネ関連などの案件受託につながった。また、基盤事業改革により案件の質的転換も実現した。VCP経営における「B:分析・構想」「C:設計・実証」機能の付加価値を高め、案件当たりの金額規模を増大させることに成功した。新常態経営も着実に進捗した。オフィス改革等による生産性の向上と経費の削減を実現し、利益面でも前年を大きく上回る結果を残した。実際、営業利益率は前年同期比1.9ポイント増の10.2%に上昇しており、高利益体質への変換が進んだ。なお、成長事業として位置付けるストック型事業も着実に進展した。インターネット出願支援サービス「miraicompass」は順調に市場を拡大した。そのほか、地域課題解決型デジタル地域通貨サービス「Region Ring」は東京丸の内、近鉄ハルカスなどの商業施設で導入が進むほか、卸電力取引のためのオンライン情報サービス「MPX」※、エントリーシート優先度診断サービス「PRaiO」なども導入実績を伸ばしたもようだ。
※同社はMPX事業を事業分割、別会社化することを2022年8月4日に発表した。
セグメント別の業績は、シンクタンク・コンサルティングサービスの売上高が前年同期比21.1%増の40,848百万円、営業利益が同21.9%増の5,359百万円、経常利益が同25.6%増の6,212百万円。ITサービスの売上高が同8.9%増の50,824百万円、営業利益が同77.2%増の3,978百万円、経常利益が同74.5%増の4,220百万円となった。シンクタンク・コンサルティングサービスにおいては、官公庁向け最先端ICTをはじめとするDX関連の大型案件が寄与し、増収増益を達成した。ITサービスでは、金融・カード分野の伸長が寄与した。売上高が伸びるとともに営業利益率も前年同期比プラス3.0ポイントの7.8%まで高まり、利益創出力が高まった。
2022年9月期期首より「収益認識に関する会計基準」を適用したことによって連結ベースの売上高が2,981百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ952百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が522百万円増加した。会計基準変更の影響を取り除いた業績値は、売上高は前年同期比10.3%増の88,691百万円、営業利益は同26.2%増の8,383百万円、経常利益は同28.7%増の9,478百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同44.6%増の7,297百万円となった。旧会計基準においても売上高、営業利益、経常利益は第3四半期として過去最高業績を達成した。
なお、同社有価証券報告書にあるとおり、主要な取引先の官公庁や民間企業の会計年度の関係により、例年3月から4月にかけて完了する案件が多く、特に第2四半期の稼働率が高くなる傾向がある。会計基準変更後は、上期に業績が偏重する傾向が強まっており、業績の季節変動要因には留意が必要である。
利益剰余金の積み上げにより、自己資本に厚み。流動比率、固定比率ともに健全で長短の流動性も良好
2. 財務状況と経営指標
2022年9月期第3四半期の財務状況を見ると、総資産は前期末比12,346百万円増加の112,051百万円となった。主な増減要因を見ると、流動資産では季節要因によって現金及び預金が13,116百万円増加し、収益認識会計基準等の適用により受取手形、売掛金及び契約資産が9,763百万円増加した一方で、たな卸資産が9,405百万円減少した。固定資産では、投資有価証券の売却によって投資有価証券が498百万円減少したほか、繰延税金資産も242百万円減少した。
負債合計は前期末比5,130百万円増加の40,998百万円となった。固定負債では長期借入金が300百万円、リース債務が650百万円減少した一方で、流動負債では買掛金が2,017百万円、未払費用が3,291百万円、未払法人税等が1,859百万円増加した。純資産合計は前期末比7,216百万円増加の71,053百万円となった。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、利益剰余金が7,084百万円増加した。
経営指標を見ると、自己資本比率が5割を超えているほか、流動比率が271.5%、固定比率が62.0%と長短の手元流動性に問題がないことが窺える。このことから財務状況は良好な状況にあると言えるだろう。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 清水陽一郎)
《EY》
提供:フィスコ

 米株
米株