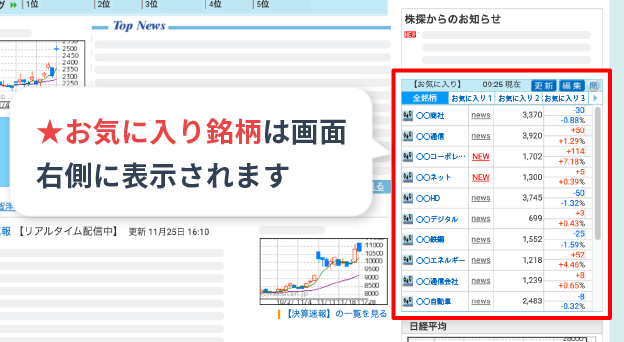iーplug Research Memo(4):企業起点で個別最適なマッチングを実現する「OfferBox」
■i-plug<4177>の事業概要
1. OfferBox
「OfferBox」は採用したい学生に、企業が直接アプローチできる新卒ダイレクトリクルーティングサービスである。「OfferBox」の企業側のビジネスフローとしては、自社のプロフィール等(企業情報や採用担当者の紹介文など)を入力した後、検索機能を利用し学生を検索する。気になる学生を見つけたらプロフィールを確認し、学生に説明会や面接への参加を促すオファーを送る。学生がオファーを承認したら少人数座談会や個人面談などに招待し、選考の中で企業と学生とが相互理解を深めた後、入社合意の確認をする。
(1) 「OfferBox」の競争優位性
「OfferBox」の特長は、業界初のオファー送受信数制限、企業からアプローチする仕組み、豊富な学生プロフィール情報、行動データを用いた機械学習、適性検査結果を含む多様な検索軸、決定に導くナレッジと支援体制、成功報酬型×低価格、など多岐にわたる。一方、こういった仕組みは模倣可能であり、現に類似サービスも出てきているが、その中で「OfferBox」が高い成長性を実現できているのには理由がある。「OfferBox」の競争優位性は、サービス提供10年で構築した独自のモデルとそれを可能にした文化にあると言える。
a) 起点の違い
新卒採用市場において、就活生は卒業に伴い毎年入れ替わるため、各学生にとって就職活動は一度きりの活動である。一方で、企業は毎年新卒採用を行っているため、新卒採用に関するナレッジが蓄積されやすい状態にある。このため、就職活動を行う学生と企業との間には情報格差があり、情報の非対称性が生じやすい構造となっている。
上記の特徴がある中、就職ナビ等のエントリー型のサービスは学生から企業にアプローチするのに対し、「OfferBox」等のダイレクトリクルーティング型は企業から学生にアプローチするという起点に違いがある。
就職活動に対して情報量及び経験量が多い企業から学生に対してアプローチするモデルであるからこそ、企業はエントリー型サービスで会うことができない学生を見つけることができ、また情報の非対称性を解消することができるため、個別最適なマッチングを生むことができている。
b) 構造の違い
これまで多くの就活生及び企業に利用されてきたエントリー型の就職ナビサイトにおいては、企業と比べて情報量及び経験量が少ない学生からアプローチするサービスであったため、認知度やブランド力の高い企業に対して応募が集まる傾向にあった。一方、企業側も応募学生について偏差値や在籍大学といった学歴などで選別する傾向があった。このようにエントリー型サービスは、特定の軸を頼りに確率論的にマッチングを発生させる構造にあった。
一方で、ダイレクトリクルーティング型の「OfferBox」においては、学生の充実したプロフィールにより学生の魅力を引き出すことに加え、企業起点によるアプローチにより、多様なマッチングを生み出せる構造にある。
c) 要所の違い
従来のエントリー型サービスにおいては、確率論的にマッチングさせていく構造であったため、いかに多くの企業と学生をサービス内に集めるか、がポイントとなるモデルであった。
他方、ダイレクトリクルーティング型サービスにおいては、1名1社ごとの個別最適なマッチングを生み出すモデルであるため、サービス登録者(社)を「増やす」ことよりも、サービス登録者をいかにサービス内で「動かす」※か、が重要であり、同社はそれに向けて日々サービス改善に取り組んでいる。
※企業においては学生を検索しオファー送信すること、学生においてはログイン・プロフィールの充実化・企業からのオファーへの返信等を指す。
さらに、一見すると模倣可能なこの「OfferBox」のモデルをユニークなものにしているのが同社の企業文化である。ミスマッチを解消するという強い信念のもと、業界初のオファー送受信数制限機能のサービスへの実装や、決定人数をKGIとしたKPIツリーを用いた改善の積み重ね、導入企業への1to1コミュニケーションの必要性を啓蒙し「動かす」オンボーディング活動への投資により、就職ナビ等の従来型モデルが築いてきた採用慣行に変化を生じさせるに至った。「OfferBox」のモデルと企業文化とが相互に影響し合うことによって、競争優位性を高めていると言うことができる。
(2) 収益の特徴
「OfferBox」には成功報酬型と早期定額型という2つの料金体系がある。同社は、成功報酬型を入口に独自の営業マーケティングによってリピート利用企業数を伸ばし、安定収益源となる早期定額型を着実に増やしている。成功報酬型は、3月1日の採用広報解禁日からオファー送信ができ、入社合意に至った時点で費用が発生する。導入のための費用がないうえ、入社以前に学生が内定を辞退した場合に成功報酬を返金する契約となっており、はじめてダイレクトリクルーティングを利用する企業にとって利用しやすいという特長がある。早期定額型は、学生3年次のインターンシップへの参加促進など採用広報解禁以前からオファー送信ができる。また、契約時に利用料金と採用枠料金を一括して支払うことで、1人当たりの採用単価を低く抑えることができる。料金は内定辞退が生じた場合でも返金しない契約となっているが、採用単価が安く、長期間サービスを利用できるため、採用の可能性を高めることができる。成功報酬型で成果を得た企業が、翌年度から早期定額型を利用するケースが多くなっている。なお、成功報酬型の場合、採用決定時に一括して売上を計上するのに対し、早期定額型は利用料金が3年次の契約から4年次の利用終了までの期間に按分されるため、翌期の売上となる料金については当該期は契約負債(前受収益)として計上される。したがって、投資を強めると当該期の費用が立つ一方契約負債(前受収益)も大きくなるため、利益率が下がる傾向がある。一方で、料金が受注時に一括入金されるため、営業キャッシュ・フローは営業利益に対して大きくなるという傾向もある。このため「OfferBox」は、安定した顧客基盤と収益基盤を生み出す仕組みになっていると言うことができる。
(3) 「OfferBox」のパフォーマンス
登録企業数は順調に増加し続け、2022年3月期末時点で10,665社(前期比31.6%増)となった。また、登録学生数も2022年卒190,538人、2023年卒(2022年3月末まで)170,748人と、コロナ禍の影響で2022年卒の登録が急増した反動で2023年卒の伸びがやや低く見えるが、増加トレンドは順調に維持できている。つれて、アクティブユーザーも増加しており、「OfferBox」は新卒人材採用のプラットフォームとしてのポジションを確立したと言えよう。
採用決定へ向けては、「動かす」ことが奏功して稼働企業数が増えており、2022年卒のオファー送信件数は前卒業年度比61.0%増と高い成長性を継続した。2022年卒においては、新規利用企業数が増加した影響もあってオファー承認率は微減(同1.6%減)となったが、採用決定人数に直結するオファー承認件数は同48.8%増とオファー送信件数同様高い伸びを継続した。なお、2023年卒の3月末時点での累積オファー承認件数も、2022年卒の同期比47.5%増と高い成長となっている。以上の結果、2022年卒の最終的な決定人数は5,027名(前卒業年度比41.7%増)となり、過去7年間の決定人数の平均成長率は70%を超えるなど、「OfferBox」を通じて就職が決定する学生数は非常に順調に伸びている。また、利用継続企業の満足度も高まっているようで、利用継続企業の平均取引額は年々拡大する傾向にあり、同社の収益性向上につながっているようだ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)
《YM》
提供:フィスコ

 米株
米株