【特集】超高齢化社会ニッポン、人生の最期彩る「終活ビジネス」関連株に照準 <株探トップ特集>
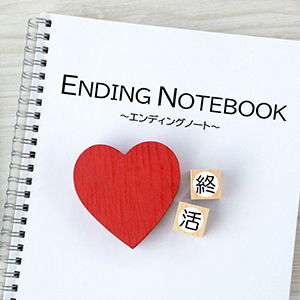 高齢化の進展に伴い、国内の死亡者数は過去最多を更新している。これに加えて、核家族化などを背景に終活への関心は高まっており、関連ビジネスの裾野も拡大中だ。
高齢化の進展に伴い、国内の死亡者数は過去最多を更新している。これに加えて、核家族化などを背景に終活への関心は高まっており、関連ビジネスの裾野も拡大中だ。―葬祭市場は実質的な縮小傾向も周辺事業の裾野広がる、葬祭DXも拡大へ―
2023年の合計特殊出生率が1.20と過去最低を更新したことを受けて、 「少子化」への関心が高まっている。特に、初めて1を割り込み0.99となった東京都では危機感が強まっており、7月7日に投開票が行われる都知事選挙でも、各候補が対策の強化を打ち出し、争点の一つともなっている。
その少子化と並んで進展しているのが「高齢化」だが、核家族化で高齢者自身が自分の最期をより良いものにしようとする「終活」に引き続き高い関心が集まっている。都知事選で「少子化」が話題となるなか、その一方で注目される「高齢化」に関連する話題として「終活」に焦点を当ててみたい。
●日本の死亡者数は過去最多を更新
総務省統計局によると、23年10月1日時点の日本の総人口は1億2435万2000人で、前年に比べて59万5000人(0.48%)の減少となった。総人口は08年に1億2808万4000人となったが、これをピークに減少傾向に転じており、11年以降は13年連続で減少している。
一方、年間死亡者数は第2次世界大戦直後である1947年に113万人を数え、その後は公衆衛生の向上や医療の進歩などで減少していたが、80年代からは増加傾向となり、2003年には100万人を突破。23年には157万5936人と前年に比べて6886人(0.44%)増加し、過去最多を更新した。
●葬儀売上高は回復傾向もピーク更新には至らず
人が亡くなると必要になるのが 葬儀だ。経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると、葬祭業主要社の売上高は年間死亡者数が戦後再び100万人を突破した03年には3646億円だったが、17年にはピークの6112億円に拡大した。
コロナ禍で20年には急減し、その後売上高は回復傾向にあるものの、近年ではコロナ禍をきっかけにして葬儀のあり方を見直す動きが強まっている。最近では、家族や近しい親族などのみで式を執り行う小規模の「家族葬」が葬儀のスタンダードとなりつつあることから、葬儀単価は伸び悩んでおり、売上高もピークを回復するまでには至らず23年は5945億円となった。ただ、取扱件数は03年の24万3904件から23年には50万1533件と初めて50万件を突破するまで拡大しており、着実に増加している。
●市場規模は実質的になだらかな縮小傾向
将来的にも、葬祭市場は厳しい環境となりそうだ。矢野経済研究所(東京都中野区)が23年9月に発表した「葬祭ビジネス市場に関する調査を実施(2023年)」によると、23年の葬祭ビジネス(葬儀費用、飲食費、返礼品)の市場規模は、事業者売上高ベースで前年比5.0%増の1兆7273億円と推計されている。コロナ禍の影響により20年は市場規模が前年比で約2割消失したものの、21年以降は回復傾向にあるという。
ただ、9年後の32年は1兆7684億円と予測しており、23年比で2.4%の伸びにとどまる見通しとなっている。死亡者数は今後も増加するものの、葬儀形式は大人数・高単価の「一般葬」から少人数・低単価の「家族葬」「直葬・火葬式」「樹木葬」などへの移行が進んでいる。葬儀単価は死亡者数の増加を上回るペースで下落するとみており、実質的にはなだらかな縮小傾向にあると予測している。
●「終活ビジネス」の裾野広がる
葬祭市場の頭打ちが予想されるなか、注目されているのが「終活」や「葬祭DX」などの新たな取り組みだ。
全国に5000社以上あると言われている葬儀会社は、地元密着型の小規模の会社が多い。また、主な顧客が高齢者ということもあって、これまでIT化や効率化が進んでいなかった。葬儀単価が下落するなか、利益を確保するためには業務効率化は急務で、DXの導入が求められている。
また、高齢化社会が進展する一方で、核家族化や若年層の減少などにより、家族や親族間での終活の支援が難しくなっていることから、自分自身や家族の最期に関する関心も高まっている。こうした「終活」を支援する新たなサービスや商品なども次々と登場しており、これら「終活ビジネス」の裾野が広がっている。
●鎌倉新書などに注目
終活関連の代表格といえば鎌倉新書 <6184> [東証P]だろう。終活に関するさまざまなポータルサイトを運営しており、「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などを展開。また、相続手続きの無料相談と専門家を紹介する「いい相続」や、介護施設・老人ホーム紹介サイト「いい介護」といった生前領域のサービスにも注力するほか、自治体の終活サービスを支援する官民協働事業も順調に拡大している。27年1月期に売上高120億円(25年1月期予想72億5000万円)、営業利益25億円(同11億円)を目指す中期経営計画では、生前領域でのサービス開発に注力する方針だ。
アスカネット <2438> [東証G]はフューネラル(葬儀)事業として、全国の葬儀社をネットワークでつなぎ遺影写真など画像映像のデジタル加工処理や通信出力サービスを提供している。また、インターネットを活用した訃報配信サービス「tsunagoo(つなぐ)」では、WEBによる記帳や香典の受け付けなども可能で、3000以上の葬儀会館に利用されている。
マネーフォワード <3994> [東証P]は相続に関する課題解決を目指すサービスとして「マネーフォワード お金のバトンβ」の提供を昨年9月に開始した。デジタルツールによる見える化とプロへの相談環境を提供することで、問題解決を支援する。
アイティフォー <4743> [東証P]は今年1月から3月にかけて、chaintope(福岡県飯塚市)と共同で、ブロックチェーンを活用した電子終活ノートの検証事業を実施した。検証の結果、終活ノートという堅牢性・真正性が求められるサービスに対してブロックチェーンが有効であることや、紙の終活ノートに比べアプリでは情報の保管や共有を容易かつ安全に行うことが可能であることを実証。これを受けて、市場化に向けて取り組みを進めている。
ブロードマインド <7343> [東証G]は個人の保険、住宅ローン、資産運用、老後資産形成や、法人の財務対策などファイナンシャルプランニングに係るコンサルティング業務を展開している。23年6月からは「終活・相続サポートサービス」をスタートさせており、財産管理や遺言書作成から葬儀場探し、遺品整理などまで各専門家と連携して一括サポートしている。
バリュークリエーション <9238> [東証G]は不動産DX事業の一環として、近くの解体業者の見積もりを比較できるサイト「解体の窓口」を運営している。終活で焦点の一つになるのが自宅の扱い方だが、同サイトは物件情報と物件写真を提出すると、付近の解体業者が次々に安い見積もり金額を提示する逆オークションが特徴で、空き家規制の強化もあって事業は成長中。更に解体後の土地活用や相続など周辺ニーズに応えることで、更なる拡大を目指している。
東京電力ホールディングス <9501> [東証P]子会社の東京電力エナジーパートナーは、22年から「さいごまで安心サービス」を提供している。生前から亡くなった後の手続きまでを一括サポートするサービスで、エンディングノートの作成アドバイスからライフプラン、資産活用、相続対策などを相談できるほか、葬儀の手配や死後の公共サービスの解約までを支援する。
このほか、上場する葬儀会社の平安レイサービス <2344> [東証S]、ティア <2485> [東証S]、こころネット <6060> [東証S]、サン・ライフホールディング <7040> [東証S]、きずなホールディングス <7086> [東証G]、ニチリョク <7578> [東証S]、燦ホールディングス <9628> [東証P]や自宅葬専門の葬儀社である鎌倉自宅葬儀社を子会社に擁するカヤック <3904> [東証G]などにも注目したい。
株探ニュース

 米株
米株










