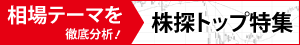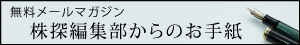【市況】武者陵司 「驚愕の日本企業収益性向上、その秘密と持続性」(後編)
 武者陵司(株式会社武者リサーチ 代表)
武者陵司(株式会社武者リサーチ 代表)―日本が打ち立てた企業内国際分業モデルの威力―
※武者陵司 「驚愕の日本企業収益性向上、その秘密と持続性」(前編)から続く
武者陵司(株式会社武者リサーチ 代表)
(3)日本企業が築いたグローバルビジネスモデル、海外が巨大なプロフィット・センターに
日本企業の海外部門の収益寄与がいかに大きくなっているか。以下では経済産業省海外事業活動基本調査(海外事業活動をしている6500社からアンケートを得ており、カバレッジと信頼性は高い)から全体像を探ってみる。残念ながらこの統計は2016年度が最新であり、直近の2017、2018年の法人企業統計における経常利益率上昇の直接の要因分析にはつながらないが、以下の分析を見れば、最近の利益率向上に、海外部門が大きく寄与していることは、ほぼ明らかであろう。
●守りの海外進出から攻めの海外進出へ
日本の製造業の海外進出は1980年代、貿易摩擦と 円高に対応した、電気機械と自動車産業の北米、アジア進出から始まった。特にアジア進出は現地の安価良質の労働力確保が最大の狙いであり、いずれも守りの進出であったといえる。
しかし、低賃金追求要因は2007年の32%から2016年には16%まで低下しており、代わって市場確保と最適生産といった攻めの要因が海外進出の動機になっている。海外生産比率(海外進出企業における)は1980年代の10%台、1990年代の20%台から、直近ではほぼ4割に上昇した。また、海外雇用人員は、2010年代に入りほぼ550万人で頭打ちとなっており、日本企業のグローバル・サプライチェーンはほぼ確立し終えたとみられる。
●海外が巨大なプロフィット・センターに
摩擦、円高などのリスク回避から出発した日本企業の海外拠点は、今や巨大なプロフィット・センターとなっている。製造業の海外法人経常利益額を国内法人経常利益合計額と比較すると、海外利益の比重が著しく高まってきたことがわかる。
1993年にはわずか製造業3.8%(全産業1.4%)であった経常利益の海外対国内比率は、2000年に製造業10.3%(全産業8.8%)、2005年製造業18.1%(全産業14.7%)、2010年製造業27.4%(全産業23.4%)、2016年では製造業27.9%(全産業16.2%)と大きく充実してきた。しかも、国内利益には海外子会社からの配当、ロイヤルティなどの支払いが含まれている。2016年度に製造業企業が海外子会社から受け取った収益はロイヤルティ2.2兆円、配当金2.6兆円、その他を含め合計5兆円にのぼる。国内製造業の経常利益合計(法人企業統計)は24.4兆円であったので、そこから5兆円を差し引けば、製造業の純国内経常利益は19.5兆円となる。他方、製造業の海外子会社の経常利益合計は6.7兆円であるが、親会社への支払いロイヤルティ2.2兆円を戻して加えれば8.9兆円となる。
こうして製造業にフォーカスすれば、国内の親対海外の子の利益比較は2対1の割合となる。加えて、国内親会社は海外子会社向け販売で当然マージンを得ている。それらを考慮すれば、今や日本の製造業企業の利益の半分近くは海外部門が稼いでいる、と言って過言ではないだろう。
(4)日本企業ほどビジネスモデルを大転換した国はない
●日本が開いた企業内国際分業モデル
過去20年間に日本ほど、価値創造の仕組み(=ビジネスモデル)を転換させてきた国はないだろう。それは国際分業とのかかわりの決定的な変化と換言できる。2000年までは、輸出主導、価格競争力主体のかかわりであった。しかし、貿易摩擦と円高でその基礎が根底から否定され、2000年前後には国難に等しい価値創造モデルの崩壊に遭遇した。そこから、新たに立ち直ったのである。
その第一の要因は技術品質に特化した非価格競争、Only One商品への大シフト、第二の要因は海外現地生産を含むグローバル・サプライチェーンの確立である。各国で最適立地に基づいて工程間分業を展開し、日本の本社が全体をオーガナイズする、という企業内国際分業体制は、日本において最も発達したビジネスモデルといってよい。その証拠がいたるところに現れている
1).巨額の一次所得収支の黒字→日本の貿易黒字はごく小さく、日本の経常黒字の大半は一次所得収支によって稼がれている。一次所得収支黒字とは現地で投資、雇用など産業活動を実施した結果生み出されたものなので歓迎されるはずのもの。他方、貿易黒字は現地での雇用を奪うという側面はあるので非難される理由はある。
巨額の一次所得収支黒字は日本企業が国際化、グローバル・サプライチェーン構築で他国を圧していることを示している。東アジアがスマホ、パソコン、テレビ、半導体、液晶などハイテク生産の世界拠点の地位を確立したのは日本企業の企業内国際分業モデルが大きく寄与している。
2).製造業では世界最低の関税率→トランプ氏は究極の理想はゼロ関税(No tariffs no barriers)と宣言しているが、その最大の恩恵は日本にもたらされるだろう。
3).日米産業補完関係→日本はかつて、半導体・エレクトロニクスなどの分野において米国の産業基盤を脅かし、それが日米貿易摩擦を引き起こしたが、今では日本は半導体やスマートフォン、インターネットインフラ、航空機などの基幹産業部門では、ほぼ全面的に米国企業に供給を仰いでいる。
他方、自動車や機械、ハイテク素材・部品など日本優位の分野では、日本企業が米国でプレゼンスを発揮している。しかも、日本自動車メーカーは米国現地生産を大きく増加させ、米国での自動車産業集積を支援した。トヨタ自動車 <7203> のGMへの生産技術供与(合弁のNUMMI設立など)、米国Big3に対して支援を惜しまなかった。摩擦対象たりえない。
4).いち早く脱中国展開→2012年の尖閣諸島の国有化以降、日本はいち早く脱中国を展開。アジア一帯で工程間分業を構築している。2012年までは日本は世界最大(除く香港)の対中直接投資国、全体の18%のシェアを持っていた。しかし、その後、各国が対中投資を増やす中で日本は大きく抑制。2017年は2012年比半減、シェアは10%、順位は4位に後退している。日本企業が世界に先駆けて、中国への過度の依存を修正したことは、海外現法設立に占める中国の比率の急低下に如実に表れている。
●熾烈な円高局面を日本企業は生き抜いた
主要先進国の労働生産性、労働報酬、単位労働コストの推移比較をみると、生産性では他国と同等の成績を上げてきた日本は、賃金の長期抑制(=停滞)によりユニットレーバーコストを大きく抑制してきたことがわかる。つまり、日本企業は世界最高のスリム化を実現してきたのである。そうして捻出した超過利潤が、円高とデフレにより販売価格が継続的に下落する中でも、モデル転換投資を可能にしたといえるが、その副作用が長期デフレであった。
それにしてもなぜ日本の労働報酬は、かくも叩かれ続けたのか、労働者は犠牲を強いられたのだろうか。その原因は円高にある。主要国製造業の賃金をドルベースと各国通べースとでみると、日本の賃金は円ベースでは停滞していたものの、ドルベースでみれば円高のために各国並みに上昇していたことがわかる。日本企業は価格競争力に耐えるために、賃金抑制を強めざるを得なかった。それでも間に合わずにグローバル展開を迫られたのである。
●大転換した日本企業のビヘイビア
こうしたことの結果、日本企業の輸出行動様式が大きく変化している。2000年代の初めの円安局面(2000年以降)では円安下でドル建て値下げが実施されたために、輸出数量が増加した。他方、円ベースでの輸出価格は全く上昇しなかった。
それに対して2013年以降の円安局面では、ドル建て輸出価格が維持され、円建てでは大幅な価格上昇が実現した。しかし、ドル建ての輸出価格は引き下げられず、価格競争力に変化が生まれなかったため、輸出数量はあまり増えなかった。かつての日本企業の得意手であった円安下での輸出ドライブは、日本企業の行動様式から完全に姿を消したのである。
(2018年9月19日記 武者リサーチ「ストラテジーブレティン208号」を転載)
株探ニュース

 米株
米株