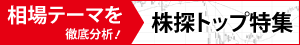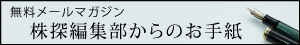【特集】【緊急特集】② 日経平均最高値更新、「5万円突破」の未来へ問われるニッポンの覚悟<株探トップ特集>
 バブル期と比べ日本企業の時価総額の上位の顔ぶれは大きく変化したが、スタートアップ企業が成長するための環境整備はなお途上段階。成長へのアニマルスピリットも、EPSの上昇を伴った株高に求められることとなりそうだ。
バブル期と比べ日本企業の時価総額の上位の顔ぶれは大きく変化したが、スタートアップ企業が成長するための環境整備はなお途上段階。成長へのアニマルスピリットも、EPSの上昇を伴った株高に求められることとなりそうだ。―バブル崩壊後の34年間でマーケットと日本企業は大きく変化、更なる成長へ課題克服なるか―
日経平均株価が過去最高値を突破した。兜町では4万円台は時間の問題とみなされ、5万円台突入を期待する強気な声さえ広がっている。確かに1989年のバブル期と比べるとバリュエーション面で割高感は乏しく、そもそも日本株は世界的には出遅れていた。しかし低金利環境のなかで過剰流動性に支えられた株高が未来永劫、継続するという確証など存在しないのも確かだ。未踏の域で持続的に株価が水準を切り上げていくうえで、日本経済と日本企業に残された「宿題」は多く、本物の成長に向けた変化の覚悟が試される局面を迎えている。
●バブル後遺症からの復活
日経平均株価は22日、前日比836円52銭高の3万9098円68銭で取引を終えた。89年12月29日につけた終値ベースでの過去最高値(3万8915円87銭)とともに、取引時間中の高値(3万8957円44銭)も上回った。
年始からの急ピッチな株高で短期的な過熱感が高まった状態だが、市場参加者からは冷静な受け止めも多い。単体決算だった89年と連結会計導入後の現在とは単純に比較できないものではあるものの、89年12月時点の東証1部のPBR(株価純資産倍率、東証公表ベース)は5.4倍に対し、2024年1月時点のプライム市場のPBRは、時価総額を加味した加重ベースで1.5倍と、大きな開きがある。経済の体温計の役割を担う金利の水準をみても、89年末の長期金利(東証上場国債10年物最長期利回り)は5.75%と、0.7%台の今とは比べものにならない高水準だ。
「半導体関連に依存した過熱感の強い相場となっているが、大局的にみて日本株がここまで上昇したのは、割安なバリュエーション面での評価が修正されつつあるためだ。PBRが1倍を下回った上場企業も依然として多く、資本効率の改善余地は大きい」(水戸証券投資顧問部チーフファンドマネージャーの酒井一氏)との声が出ている。
およそ34年の間、日本はバブル崩壊を受けた後遺症に苦しみ、金融システム危機やリーマン・ショック、東日本大震災も経験した。経済のグローバル化の進展に伴って、「日本人の日本人による日本人のための」マーケットからの脱却も余儀なくされ、日本株は海外投資家の売買動向による影響を大きく受けるようになった。日立製作所 <6501> [東証P]の株主構成比率をみても、「外国法人等」は50%に迫る水準だ。
バブル崩壊後は、マーケットが政治に及ぼす影響力を印象付けた期間でもあった。カブを手に「株よ上がれ」とおどけてみせた小渕恵三元首相、「バイ・マイ・アベノミクス」と訴えた安倍晋三元首相。岸田文雄現首相も海外投資家を前に「インベスト・イン・キシダ」と語っている。政府サイドにとって株安を回避する手段の一つが、低金利環境の醸成、すなわち金融緩和策である。98年の改正日銀法施行により政府からの独立性を高めた日銀は、13年に政府とアコード(共同声明)を結び、インフレ2%目標の達成へ異次元の緩和策を遂行した。
バランスシート不況を経て構造改革に努めた日本企業が収益力を着実に高めるうえで、金融緩和という環境面での後押しがあったのは紛れもない事実だ。今や低金利環境下で攻めの投資に向けた資金調達は容易な状況にあり、新たな事業を興し、企業価値を一段と高めるにはこのうえないステージが用意されている。
「日本企業は海外で稼ぐ力を身に付け、収益性も高まった。バブル期は日米構造協議のもと、米国は日本企業の生産拠点の海外移転を促したが、今や米中対立の流れのなかで、台湾積体電路製造(TSMC)<TSM>が日本に工場を建設する真逆の時代となっている。実質GDPが2四半期連続でマイナスになるなど国内景気は芳しくないが、明るい兆しもみられる」(三菱UFJアセットマネジメント・チーフファンドマネジャーの石金淳氏)との声がある。
●企業の新陳代謝には課題も
日本企業の時価総額上位の顔ぶれをみると、日本電信電話 <9432> [東証P]や大手銀行が中心だったバブル期とは大きく変化し、ファーストリテイリング <9983> [東証P]やソフトバンクグループ <9984> [東証P]、キーエンス <6861> [東証P]など、創業者の強力なリーダーシップのもと成長を遂げた企業が加わった。楽天グループ <4755> [東証P]やニデック <6594> [東証P]など、日本の企業史に名を残すベンチャー発企業の時価総額も大きく増加した。
一方で、ソフトバンクGの孫正義会長兼社長は60代、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は50代後半、ニデックの永守重信会長に至っては後継者を選んだとはいえ、今年で80歳だ。超氷河期世代以下の起業家が次々と現れなければならないなかで、日本の開業率は20年時点で5%程度、廃業率は3%程度と欧米諸国に比べて低水準にある。
米国市場ではアップル<AAPL>やマイクロソフト<MSFT>に続く形で、テスラ<TSLA>やアマゾン・ドット・コム<AMZN>、そしてエヌビディア<NVDA>と主役が次々と誕生している。企業の新陳代謝の進み方は、日本とは比にならない。その原動力となったのは、資本の力と強烈な個性を持つ経営者はもちろんのこと、経営者のビジョンに共感してサポートをする優秀な人材の存在も大きい。日本人中心の多様性の乏しいマネジメント体制では生まれにくい発想が、米国のグロース系企業では次から次へと浮かび上がり、実現に向けて動き出し、トップラインを伸ばしている。
●外部依存型の変化からの脱却できるか
組織理論家のリチャード・ベックハード氏が提唱した「組織変革の公式」によると、「現状への不満のレベル」と「説得力のあるビジョン」、「変化の実現性の高さ」の3つを掛け合わせた時、「変化のコスト」を上回れば、組織変革は実現する。例えば、日本企業が構造改革をするには、人的アセットの縮小時に支払うコストがあまりにも高くつくと考えられている。成長に舵を切ろうとしても、雇用の流動性は高くはなく、優秀な人的アセットを確保するのも容易なことではない。
こうした話は雇用慣行ばかりではない。企業にとって現状維持の打破というのはそもそも、大きなエネルギーが必要な作業である。ROE(自己資本利益率)の向上に向けた企業の取り組みが活発化したのも、企業側の自発的な動機というよりは、経済産業省のプロジェクトでまとめられた伊藤レポートに象徴されるような、「雰囲気」の醸成に後押しされた面が大きいのではないか。
半面、私たちは外国人がトップとなって、業績が急激に悪化した企業の事例を、バブル崩壊後にいくつもみてきた。重要なのは、外的要因に頼りきるのではなく、トップと現場のコミュニケーションにより内発的な動機づけを図ったうえで、強固な組織形成にまい進するということであり、それでこそ本当の意味で企業価値が高まっていくということである。経営陣とともに労働者側も、成長に向けた「覚悟」が求められる作業だ。
悲観的になる必要はない。日本にはグローバルでみても、自律的な成長につながる独創性の高い文化を醸成してきた企業が数多く存在する。堀場製作所 <6856> [東証P]が自動車のエンジン排ガス測定装置で世界にその名を轟かせる原動力となったのは、「おもしろおかしく」という社是に示されるような、前向きに変化を楽しむ精神だった。経営方針にクリスチャンの創業者による経営者としての歩みが紹介されている山崎製パン <2212> [東証P]は、聖書の教えを支えに事業を展開した過去を踏まえ、大規模災害時の食料供給支援を社会的使命と位置付ける。同社のトラックは、今年1月1日の能登半島地震発生後、すぐに被災地に向かった。
明確化した自社のミッションを飾り物とするのではなく、社員やステークホルダーと深く共有し、共感という無形資産であるブランド価値を高めていく。そうした日本企業が増えていくことによって、日経平均株価が未踏の域で持続的に上昇する──。日経平均株価5万円台到達へ向けた原動力が、企業の内なるエネルギーに裏付けられた予想EPS(1株利益)となることを強く期待している。
株探ニュース

 米株
米株