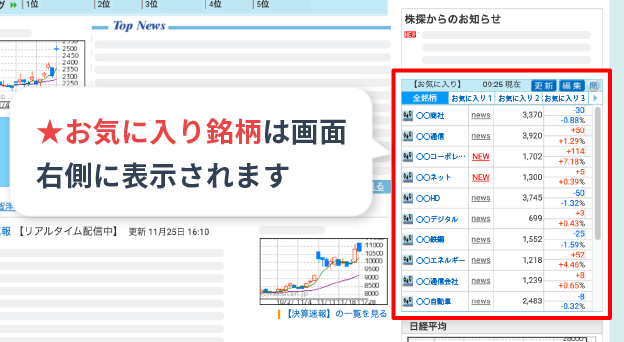テクマト Research Memo(6):情報基盤事業は採算重視の営業方針に切り替え、第4四半期に収益性が回復(1)
■テクマトリックス<3762>の業績動向
2. 事業セグメント別の動向
(1) 情報基盤事業
情報基盤事業の売上収益は前期比18.6%増の29,305百万円、営業利益は同2.3%増の3,125百万円と過去最高業績を更新した。半導体不足による一部製品の納期遅延の影響やサブスクリプション化の進展による売上の繰延傾向が続いたものの、豊富な受注残や新規受注も好調に推移したことで売上収益は2ケタ増ペースが続いた。
製品別の売上動向を見ると、負荷分散装置やストレージ製品は半導体不足による納期遅延の影響が出たものの、前期並みの水準を確保した。一方、Palo Alto NetworksのSASEと呼ばれるクラウド型セキュリティ対策製品「Prisma Access」が引き続き好調に推移し、CASB※1、Cyber Hygiene※2、SDP※3など新たなセキュリティ対策製品も伸長した。次世代メールセキュリティ製品についても、メール経由でのウィルス感染が拡大するなかで好調を持続した。また、セキュリティ運用・監視サービス「TPS(TechMatrix Premium Support)」については受注の期ズレにより計画を下回ったものの、売上収益は2ケタ増と好調に推移した。
※1 CASB(Cloud Access Security Broker):クラウドサービスのユーザとプロバイダーの間に位置し、クラウド利用状況の可視化や制御を行い、全体として一貫性のあるセキュリティポリシーを実施できるようにすること。
※2 Cyber Hygiene:定期的なパスワード変更やソフトウェアのアップデートなど、ユーザ単位でIT環境を健全に保つための取り組みを行い、セキュリティ・インシデントを防ぐこと。
※3 SDP(Software Defined Perimeter):ネットワークを経由した様々な脅威に応じた境界線をソフトウェア上で構築し、アプリケーションインフラや機密情報への柔軟なアクセス制御を可能にするセキュリティフレームワークのこと。
受注高は、サイバー攻撃が頻発化するなかで企業や自治体のセキュリティ対策強化の動きが続き前期比35.7%増の40,618百万円と大幅増となった。期末受注残高もサブスクリプション型のクラウド型セキュリティ対策製品(複数年契約)の引き合いが好調だったことから、前期末比43.7%増の37,214百万円となった。顧客属性については、従来グローバル企業がほとんどであったが2023年3月期は中堅企業や自治体からの受注も増え、顧客の裾野が広がってきた。自治体については、従来は地元のSIerからオンプレミス製品を導入するケースが多かったが、ITシステムのクラウドシフトが進むなかでセキュリティ対策製品もクラウド型を導入する動きが広がり、同社が受注するケースが増えたものと見られる。
営業利益については第2四半期までの為替の急激な円安進行による影響や人件費及び販管費の増加、案件の大型化による採算性の低下、新規事業(クラウドネイティブ活用ソリューション)への投資などが影響して若干の増益に留まった。四半期ベースで見ると第3四半期までは小幅な増益が続き、営業利益率も10%を下回る水準で推移していたが、夏場以降に採算重視の方針に切り替え営業活動を徹底した効果で、第4四半期の営業利益は前年同期比19.6%増と増益に転じた。利益率も14.1%と前年同期を上回る水準まで回復した。なお、為替変動リスクについては、受注が決まった際の為替レートで契約期間分の利用料金(売上収益)や海外ベンダーへの支払額も固定化するため基本的にはないが、商談時に為替レートが円安局面にある場合は顧客側から見ればコスト高となるため、値下げ圧力が強まる可能性は考えられる。特に、複数年契約している顧客が契約を更新する際には、その傾向が強くなることが予想される。
子会社の業績動向について見ると、クロス・ヘッドはインフラ構築案件の受注が堅調に推移したことにより、受注高、売上収益、営業利益ともに会社計画を上回った。また、OCHは主力製品の一部において競争が激化した影響で売上収益・営業利益ともに計画を若干下回ったが、リモートデスクトップ・サービスや自社企画製品・サービス等のサブスクリプション課金モデルの事業については順調に拡大し、ストック型ビジネスへの転換が進んだ。
なお、情報基盤事業(単体)におけるストック割合は、サブスクリプション課金モデルであるクラウド型セキュリティサービスの拡大を背景に2021年3月期以降急上昇し、2023年3月期は77.4%と売上の大半を占めるまでになった。今後もサブスクリプション課金モデルのサービスが主流となることから、着実な売上成長と安定した収益が続くものと予想される。
(2) アプリケーション・サービス事業
アプリケーション・サービス事業の売上収益は前期比0.8%増の7,300百万円、営業損失は20百万円(前期は48百万円の損失)となった。受注高も同0.1%増の7,801百万円と横ばい水準に留まったが、期末受注残高は同12.7%増の4,458百万円と増加した。
分野別の売上動向について見ると、ソフトウェア品質保証分野はサブスクリプション型のライセンス契約増加により、売上計上が繰延傾向となったものの、企業向けシステムや組込ソフトウェアの品質を担保するテストツールの需要が好調に推移し、前期比で2ケタ増収となった。また、教育分野も規模はまだ小さいながらも主体的な学びを実践する先進的な私立高校や公立校への導入が進み、会社計画を上回る受注となった。CRM分野はサブスクリプション化の進展により売上計上が繰延傾向となったほか受注の遅れもあって会社計画は未達となったものの、前期並みの水準は確保した。ビジネスソリューション分野は受注の遅れにより計画未達となったが前期比横ばい水準となった。カサレアルは技術者向け新人研修の好調により会社計画を超過し、前期比でも増収となった。アレクシアフィンテックはリスク管理ソリューションにおいて金利指標となっていたLIBORの廃止に伴い発生したリプレイス需要が前期で一巡した反動により会社計画、前期比ともに下回った。
利益面ではビジネスソリューション分野で一部不採算案件が発生したこと(第3四半期で収束)、教育分野で4月の一斉納品に向けてエンジニアを増員したことなどがマイナス要因となったが、CRM分野で広告宣伝費を削減したことにより若干の損失縮小となった。
アプリケーション・サービス事業(単体)のストック売上比率については62.4%となった。前期はストック型ビジネスモデルである旧NOBORIの数値を含めて60.0%(旧NOBORIを除けば約50%)だったため、実質的な上昇率はもう少し高かったことになる。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
《YI》
提供:フィスコ

 米株
米株