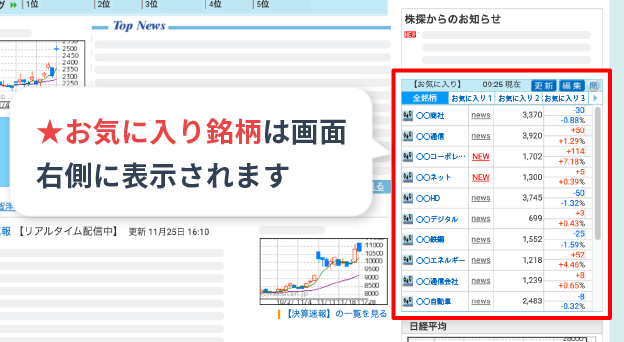紀文食品 Research Memo(5):厳しい事業環境の下でも、売上拡大 海外食品事業セグメントが2ケタ増益(1)
■業績動向
1. 2023年3月期第2四半期累計の業績動向
紀文食品<2933>の2023年3月期第2四半期累計(2022年4月-9月)の業績は、売上高で前年同期比10.0%増の46,788百万円、営業利益で-786百万円、経常利益は-749百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は-1,332百万円となった。第2四半期累計としては増収減益とはなったものの、従来より利益が下期に偏重するタイプのビジネスモデルである。売上高は前年同期を大きく上回ったが、営業利益は原材料とエネルギー価格の上昇の影響を受けたため、前年同期を下回った。第3四半期以降は売上好調を維持していくとみられ、コスト上昇分については対策がとられていることから、業績は回復に向かうものと弊社では見ている。
販管費も495百万円(前年同期比5.5%)増加している。要因として、売上好調に伴う物流増加によるコスト増加があげられる。配送に関わるエネルギーコスト増加や人手不足による人件費高騰によることが要因だが、同社は費用増を抑えるため、運行便の集約による積載率の改善等の削減を行うなどの取り組みによって補うことで、配送業務の効率化を進めている。また、各経費の見直しを行い、効率化を進めたことで、販管費の増加率を売上高の増加率より抑えている。
営業損失を計上することとなった主な要因として、原材料価格の上昇による-1,345百万円があげられる。その他マイナス要因としては、生産拠点での電力・燃料費の上昇に伴うエネルギー価格の上昇による-387百万円、売上増にともなう物流費などの販管費の増加-496百万円などである。コスト上昇が続くなかで、同社は生産効率の改善で88百万円のプラス、海外販売品では利益率の高い自社製品の売上構成比率の増加で143百万円のプラス、販管費の削減、原価改善・効率化などに取り組み収益の改善に努めている。また今後、想定している以上のコスト増が続く場合は、商品の規格変更や価格改定を行い、収益改善に取り組む方針である(2022年12月16日に、2023年2月27日から価格改定を行う旨を発表)。
現在のグローバル経済はコロナ禍による経済停滞からの回復過程で、諸原材料の需給バランスの崩れと通貨の過剰流動性、ウクライナ問題による穀物や天然ガス等の供給サイドの問題が重なったために生じたと弊社は認識している。現状を見ると、欧州・米国の景気後退観測や為替相場の過熱感がいくらか解消してきたこと、またエネルギー価格も2022年夏前には120ドルを超えていたWTI原油先物価格が80ドル前後で落ち着いていることから、今後もコスト増を想定し慎重に行方を見極めているものの、2023年からコスト上昇および原油高については、徐々に落ち着きを取り戻すと弊社では見ている。
一方、プラス要因としては売上要因によるものが769百万円、国内での価格改定効果により701百万円が寄与した。同社では下期も依然として原材料価格とエネルギーコストの上昇を想定して事業を行いながら価格改定による収益改善効果を進め、第3四半期の需要拡大期に合わせプロモーション活動を連動させながら拡販を進めることで上期のマイナス分の回収を進め、通期の営業利益を確保するよう注力していく方針である。
2. 事業セグメント別業績
2023年3月期第2四半期累計のセグメント別業績は国内食品事業は売上高31,231百万円(前期比6.7%増)、セグメント利益は-1,704百万円、海外食品事業は売上高6,898百万円(前期比46.3%増)セグメント利益790百万円、食品関連事業は売上高8,658百万円(前期比1.2%増)、セグメント利益では209百万円となった。「国内食品事業」「海外食品事業」「食品関連事業」の3セグメントの売上高は前年同期を上回った。営業利益は国内食品事業が減益となり、海外食品事業については前年同期を上回る進捗となっている。また食品関連事業も営業利益は前年同期を上回る進捗となっている。国内食品事業の減益幅が大きかったため、全社では減益となった。各セグメントで需要は改善傾向にあり前年同期で売上高は増収となったが、国内原材料高を背景に利益の押し下がる構造となっている。
3. 国内食品事業
売上高は31,231百万円(前年同期比6.7%増)となった。業務用の食用油脂やゴマなどの販売が好調に推移して商事部門で売上が増加したことに加え、価格改定後でも売上比率約7割を占める主力商品である水産練り製品の販売数量増となり、売上高が約2.5億円増(前年同期比1.5%増)となり増収の要因となった。竹輪が3.3%増、カニカマが6.6%増、はんぺんが4.1%増、さつま揚げが0.9%増と主力商品が売上を伸ばした。次世代需要層に向けた主力商品のキャラクター蒲鉾や竹笛などはWeb、SNS、店頭での情報発信およびプロモーション活動により露出を高めたことにより、売上高も順調に拡大し、全体の売上を伸ばすことに寄与した。一方、コロナ禍の需要を捉えたことで前年同期は売上増加していた糖質0g麺や中華惣菜系は社会活動が平常化に向かう中で、内食需要が減少した影響で前年同期比では売上減となったが、あらたな需要層の開拓などで挽回をはかる。国内食品事業では引き続き主原料の価格高騰とエネルギー価格の上昇が、想定していた需要の反動減以上に上昇したため減益となっている。第3四半期以降もエネルギー価格上昇や原材料高騰は高止まりを想定しながら、利益率の改善に注力していく。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 石灰達夫)
《SI》
提供:フィスコ

 米株
米株